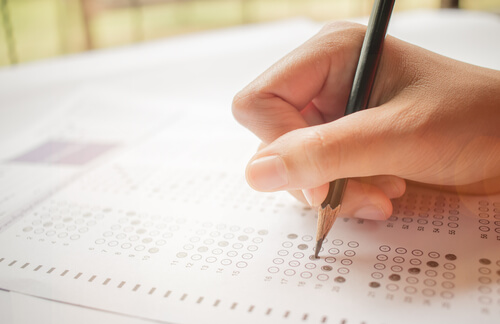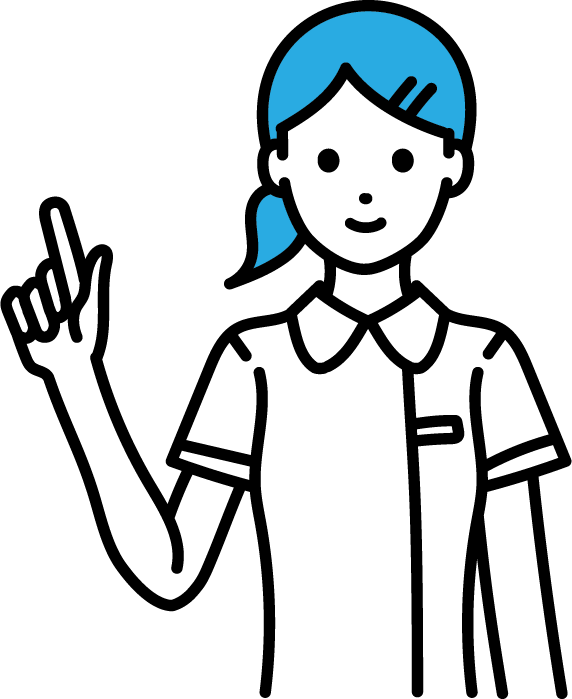HLCAライターのはなえです!
医療英語を学ぶための方法は、オンライン英会話や留学などがあります。
それに加え「資格取得」という方法もあります。
資格を目指して学習すれば、自身の英語力を客観的に示すことができ転職などに有利になります。
また、目標ができることで、英語学習のモチベーションを保てることは間違いありません。
本記事では、医療英語の代表的な資格5つを紹介します。
国際的な医療資格に興味がある、関わる英語力を最短で取得したいという方は以下からお問い合わせください!
医療英語ハルカでは、日本の医療英語資格だけでなく、海外進出を目指す医師・看護師向けのOET対策も可能です(他の職種の方もお問い合わせください)。
医療留学のプロにより無料のカウンセリングも受け付けております。
この記事のもくじ
医療英語おすすめ資格1:日本医学英語検定試験(医英検)
 日本医学英語検定試験(医英検)は、日本医学英語教育学会が主催している資格です。
日本医学英語検定試験(医英検)は、日本医学英語教育学会が主催している資格です。
日本の医療、医学を推進することを目的としています。
医療系の文献を英語で読むこと、情報を聞いて伝えること、英文で書いて表現することといった英語4技能をバランスよく評価される資格です。
ちなみに2021年は、HLCAのオンラインレッスン受講生の中から数名合格者が出ています(4級)。
対象者
医英検には、4つのレベルがあり、レベルによって受験対象者は異なります。
▼ エキスパート級(1級)
日本医学英語教育学会会員で,かつ日本医学英語検定試験プロフェッショナル級(2級)取得者に限る
▼ プロフェッショナル級(2級)
日本医学英語検定試験応用級(3級)取得者に限る
▼ 応用級(3級):特に制約はなし
▼ 基礎級(4級):特に制約はなし
まずは、基礎級である4級からチャレンジするのがよいと思います。
内容と試験時間
各級の内容は以下のようになっています。
▼ エキスパート級(1級) 面接試験:30分 医学英語あるいは医学英語教育に関する業績の事前審査
▼ プロフェッショナル級(2級) 筆記試験:80分(自由筆記3問) プレゼンテーション試験:口頭発表10分、質疑応答15分
▼ 応用級(3級) 筆記試験:90分(60問程度:語彙25問程度, 読解35問程度、マークシート選択式) リスニング試験:30分(15問程度、マークシート選択式)
▼ 基礎級(4級) 筆記試験:90分(50問程度、語彙25問程度、読解25問程度、マークシート選択式)
(引用元:日本医学英語検定試験(医英検) 試験時間と内容)
3級と4級は筆記試験のみマークシート選択式です。英語学習初心者にも比較的取り組みやすい内容となっています。
1級と2級はそれぞれ面接試験やプレゼンテーションなどがあります。こちらは、試験対策をしなければ合格が難しいと思われます。
難易度
公式サイトによると、それぞれのレベルは以下のようになっています。
▼ エキスパート級(1級) 医学英語教育を行えるレベル(プロフェッショナル級[2級]受験者を指導できるレベル)
▼ プロフェッショナル級(2級) 英語での論文執筆・学会発表・討論を行えるレベル
▼ 応用級(3級) 英語で医療に従事できるレベル(医師・看護師・医療従事者,通訳・翻訳者,等) 応用級(3級)受験者で筆記試験合格/リスニング試験不合格の場合は,「準応用級(準3級)」に認定されます。
▼ 基礎級(4級) 基礎的な医学英語運用能力を有するレベル(医科大学・医療系大学在学あるいは卒業程度)
(引用元:日本医学英語検定試験(医英検) 等級と難易度)
1級、2級を受験する場合、受験申告書に英語での論文や医療英語教育の実績について、英文履歴書(CV)へ記入して提出する必要があります。
試験日だけでなく、医療英語習得へ向けての活動まで評価される試験です。
対する3級は、英語で医療に従事できるレベル、4級は基礎的な医療英語運用を有するレベルとされており(大学在学あるいは卒業程度)、英語を得意とする学生でも合格が期待できそうです。
受験料
受験料は2022年から変更になりました。最新受験料は以下の通りです。
▼ エキスパート級(1級) / プロフェッショナル級(2級) 15,000円
▼ 応用級(3級) 9,000円(準3級合格者が,リスニング試験のみ受験する場合は3,000円)
▼ 基礎級(4級) 6,000円
すべて税込です。
2024年試験日程
2024年の3・4級の試験は、6月16日(日)に行われる予定です。
申し込み受付期間は、2024年2月15日(木)~4月11日(木)、受験会場は、北海道、東京、愛知、滋賀、大阪(2ヶ所)、岡山、福岡、佐賀となっています。
なお、1級・2級は2024年1月に終了しています。
詳しくは公式ホームページをご覧ください。
公式ページ:日本医学英語教育学会
医英検突破の勉強方など知りたい方は「医療英語に特化した英検、医英検(日本医学英語検定試験)を徹底解説!」からどうぞ。
医療英語おすすめ資格2:国際医療英語認定試験CBMS

国際医療英語認定試験CBMS(以下、CBMS)は、医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、救急救命士、その他の専門職、事務職などのスタッフが医療英語のスキルアップを図れるようにと2011年から実施されている試験です。
主催団体は、一般財団法人 グローバルヘルスケア財団となっています。
CBMSは、合格不合格で判断される試験ではなく、TOEICのように取得したスコアを認定する試験となります。
面接はなく、筆記とリスニングのみであるところも、TOEIC と似ています。
試験はCBT方式(Computer Based Testing:コンピューターを利用した試験)です。
対象者
公式サイトには、明確な対象者の記載はありません。
BasicとAdvancedに分かれているため、初めて受験する方はBasicを目指すとよいでしょう。
内容と試験時間
以下、2023年の内容です。
Advanced
リスニング試験では、会話応答問題、イラスト理解問題、会話要点理解問題、スピーチ要点理解問題が70問あります。
リーディング試験では、語彙・語法、会話理解、専門用語理解、読解を試す問題が70問出題されるようです。
試験問題はリスニング60分、リーディング60分、合計120分で、800点満点で点数がつきます。
Basic
CBMS試験と同じく、リスニングとリーディングがあります。
試験問題はリスニング30分、リーディング30分、合計60分で、400点満点で点数がつきます。
難易度
難易度に対する明確な記載はありません。
試験後は、獲得点数の証明書と得点表を受け取ることができます。
Advanced
- 英語で医療行為等の説明をスムーズかつ適切にできるか
- 外国人の医療スタッフと知識・情報をスムーズかつ適切に共有できるか
- 外国人患者・家族への基本的な案内
- 指示・連絡・介助ができるか
受験料
Advanced
国際医療英語認定試験CBMSの受験料は14,500円(税込)です。
Basic
受験料は、税込7,700円です。
2024年試験日程
現時点では未定です。
AdvancedとBasic共通で、2023年の試験日は11月11日(土)、オンラインで実施される予定です。Basicは午前、Advancedは午後と分かれています。
申込み入金期限は11月4日(木) です。
6月と9月に模擬試験がありました。試験について、詳しくは公式ホームページをご覧ください。
医療英語おすすめ資格3:医療通訳技能検定試験
 医療通訳技能検定試験は、一般社団法人日本医療通訳協会が実施している医療通訳技能の検定試験です。
医療通訳技能検定試験は、一般社団法人日本医療通訳協会が実施している医療通訳技能の検定試験です。
全員が同じ試験を受け、点数に応じて1級、2級、または不合格の判定がなされます。
もともとは、東京通訳アカデミー(閉校)の医療通訳士コースの卒業試験としてスタート。
卒業生以外も受験できるようにしようと、2014年から実施されています。
英語、中国語、ベトナム語、韓国語の4つの言語が対象で、1級と2級があります。
対象者
2級では、以下3つのいずれか1つに該当する方が対象となります(医療通訳スクールの講座修了者,医療通訳の実務経験1年以上,試験委員会が前各号と同等と認めたもの)。
1級の場合は、医療通訳の実務経験2年以上が対象です。
内容と試験時間
1次試験(筆記)と2次試験(面接、ロールプレイ)があります。
▼ 1次試験 120分、問題数は12問です。 厚生労働省の標準カリキュラムを参考として、医療知識や制度、医療通訳の倫理などについて出題されます。 点数により、1級・2級と判定されます。
▼ 2次試験 面接では医療知識・語学力・通訳力・礼儀・態度・服装等などが試されます。実技のロールプレイングの試験です。
合格の判定基準は以下のとおりです。
▼ 1級:医療全般かつがん治療などの重度疾病に通訳対応可能なレベル ▼ 2級:人間ドックや慢性疾患、中軽度疾病などに通訳対応可能なレベル
難易度
語学力の目安は、1級はTOEIC840以上、英検1級、2級はTOEIC620以上となっています。
受験料
受験料は1次試験が7,700円、2次試験が18,700円です(2024年から改訂)。 2次試験の受験料は、1次試験合格のあとに支払います。
2024年試験日程
英語に関しては、年に2回(1次試験は4月と10月、2次試験は1次試験の2ヶ月後)に実施されます。
2024年春受験の受付をしています。
それ以降の日程発表は現時点ではありません。
試験会場は次の都市のみとなっています。 1次試験:札幌・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・沖縄 等 2次試験:東京・大阪・福岡・札幌・沖縄 等
参考:医療通訳技能検定試験
医療英語おすすめ資格4:医療通訳技能認定試験
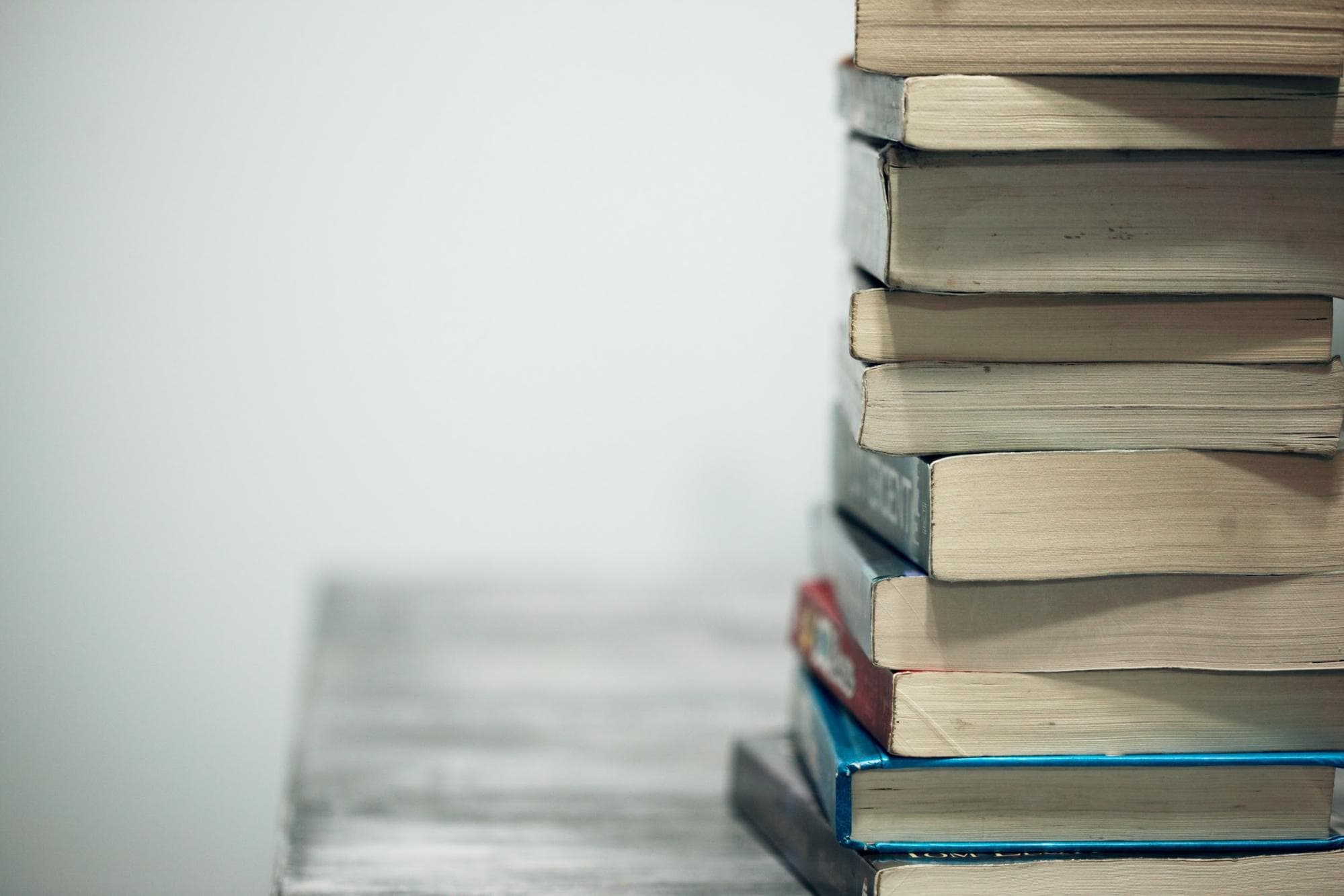
医療通訳技能認定試験は、一般財団法人 日本医療教育財団が運営する試験で、基礎と専門の2通りあります。
医療通訳に特化した内容で、英語のほか、中国語も対象です。
対象者
公式サイトによると、受験対象者(は以下のように定められています。
※(1)~(4)のいずれか一つに該当する者 (1)「医療通訳専門技能認定試験受験資格に関する教育訓練ガイドライン」に適合すると認める研修・講座等を履修した者
(2)医療通訳の実務経験を、目安の件数もしくは時間数以上有する者 [実務経験の目安] 医療通訳の実務を60件程度、もしくは60時間程度 (過去5年以内に上記経験があること)
(3)医療通訳基礎技能認定試験の合格者で、医療通訳の実務経験を、目安の件数もしくは時間数以上有する者 [実務経験の目安] 医療通訳の実務を30件程度、もしくは30時間程度
(4)認定委員会が前各号と同等と認める者
(引用元:医療通訳技能認定試験の対象者)
なお、合格者は医療通訳専門技能者(英語)という称号が与えられます。
内容と試験時間
試験は1次と2次に分けられます。
▼ 1次試験 ・筆記試験 四者択一式・選択式:60分 ・リスニング試験 選択式・記述式:20分
▼ 2次試験 ・コミュニケーション言語能力試験(対面) ・対話通訳試験(対面):1人30分程度 1次試験、2次試験ともに、各科目の得点率が70%以上であれば合格となります。
難易度
受験資格ではありませんが、医療通訳技能認定試験はTOEFL iBt 87 以上 / TOEIC 785以上のレベルが最低限必要とされています。
受験料
受験料は以下の通りです。
<基礎> ▼ 1次試験:9,000円 ▼ 2次試験:15,500円
<専門> ▼ 1次試験:11,000円 ▼ 2次試験:17,500円
2024年試験日程
基礎と専門は、1次2次試験ともに年に1回ずつの開催です。
<基礎> 1次試験:10月,2次試験:1月予定
<専門> 1次試験:11月,2次試験:2月予定 現時点では具体的な日程の記載はありません。 1次試験:基礎2022年10月22日/専門は11月19日,2次試験:基礎2023年1月28日/専門2月15日予定です。
参考:医療通訳技能認定試験
医療英語おすすめ資格5:医療英会話技能認定

医療英会話技能認定とは、医療機関の事務で求められる英会話に関する試験です。
医療通訳技能認定試験と同じく、一般財団法人 日本医療教育財団が運営しています。
対象者
医療機関の事務スタッフ向けの資格です。承認を受けた教育機関で所定のカリキュラムを習得し、修了試験に合格した方に対して技能を認定するものとなっています。
内容と試験時間
「医療英会話技能認定申請資格に関する教育訓練ガイドライン」に沿った内容が、学科試験と実技試験に分かれて出題されます。
学科試験は、医療英単語や英語表現など25〜30問、実技試験は場面ごとの英会話についての出題です。
試験時間は、学科試験50分、実技試験は1問あたり3分で2題となっています。
ガイドラインに含まれているのは、体の部位の名称の他、医療機関での場面ごとの英会話など、実践的な内容ばかりです。
難易度
公式サイトには、難易度に関する明確な記載はありません。ガイドラインを見る限り、出題範囲はそこまで広くないため、他の試験と比べると難易度はそこまで高くなさそうな印象をうけます。
得点率70%以上で合格です。
受験料
受験料は3,000円です。
2024年試験日程
公式ホームページへの記載はありません。
参考:医療英会話技能認定
まとめ:医療英語の資格を取得する目的を決め、受験する試験を選ぼう!
医療英語の資格はいくつかあります。
資格を得てどのようなスキルを証明したいのかを考えながら、受ける試験を考えましょう。
今回紹介したものの中から、それぞれの職種に適している資格をまとめました。
▼ 医師・看護師・薬剤師などの医療従事者:日本医学英語検定試験(医英検)、国際医療英語認定試験 CBMS
▼ 医療通訳士:医療通訳技能検定試検、医療通訳技能認定試験
▼ 医療事務:医療英会話技能認定
▼ 医療系の学生:CBMS Basic試験
資格取得を目指すことで、闇雲に学習を進めるよりも成果が明確に出ます。
合格したり点数が上がったりすると、医療英語に対する学習の姿勢が評価されるため、大きな喜びを感じるに違いありません。
しかし医療英語試験のような専門的な内容は、自分1人で学習するには息詰まりやすい分野なのではないでしょうか。
面接が含まれる試験対策は、一定期間集中して英語学習に取り組むのがおすすめです。
語学学校HLCAのオンラインレッスンでは、医療用語のみならず臨床英会話も学べます。
マンツーマンで医療英語に特化した授業を受けることにより、面接やプレゼンテーション能力を身につけることが可能。
1人で勉強するより、講師とともに短期集中で力をつけたほうが英語の伸びが早いのは間違いありません。
モチベーションを保ちながら一気に英語力を伸ばしたい方は、ぜひHLCAのオンラインレッスンを受講してみてはいかがでしょうか。